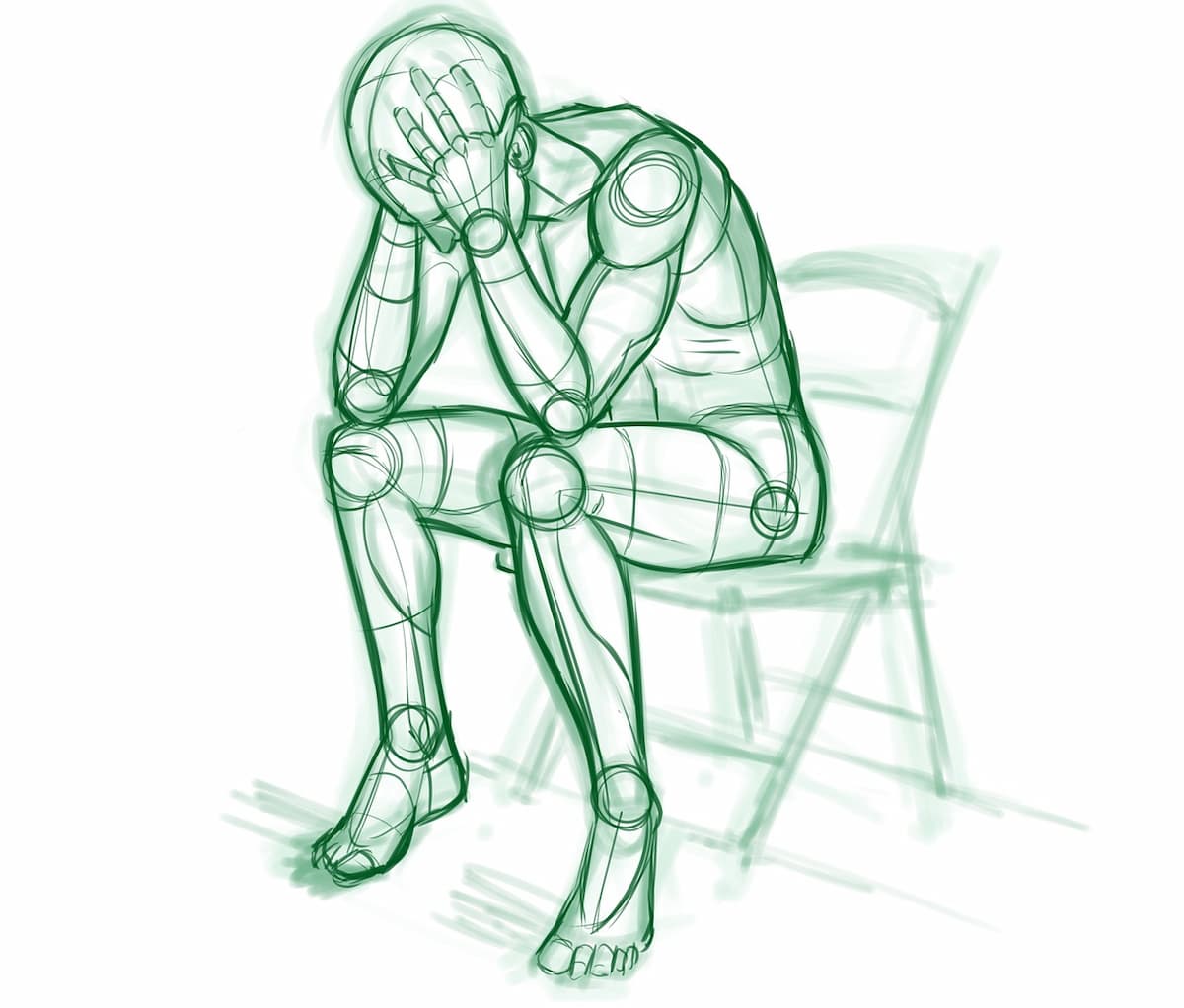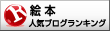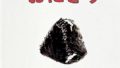悩めるお母さん
「子どもが元気が良すぎる。周りに配慮しないと。」
「子どもの声が大きい。お隣は受験を控えている学生さんがいるし、気を遣わないと。」
都市部に住んでいると、多くの方が悩まされる騒音問題。なかでも、子どもの声、叫び、ボール遊び、プール遊び、走る音、様々な子どもに関する騒音問題が存在します。
「子どもは元気だから、騒いでもいい。」
このように考えている方がいるのも確かですが、全くそのように考えていない方が多いのも事実です。
まず、子どもを持つ親は、「子どもが騒いでもいい」という認識を改めましょう。
私には、3歳の娘がいます。
独身時代には、隣家の子どもの騒音問題に悩まされた経験があります。
そのため、子どもはいるものの、子どもの騒音には人一倍気を遣っています。
それは、自分自身が苦痛を受けたので、他の人たちには同じ思いをさせたくないからです。
騒音トラブルが起きるのは、認識のズレ
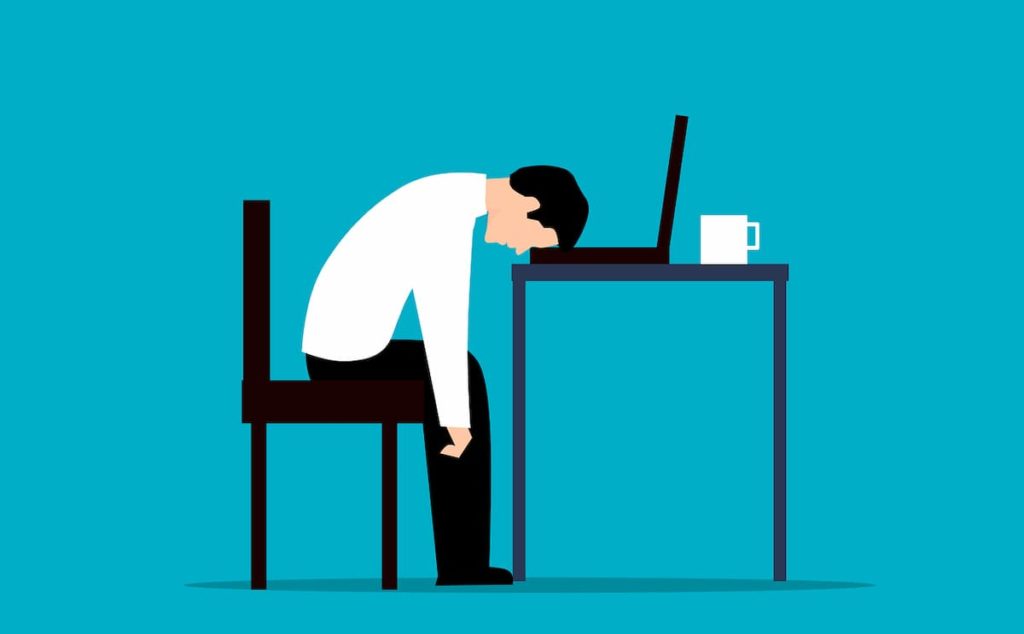
子どもに関する騒音トラブルが起きるのは、認識のズレが起きているためです。
子どものいる家庭【騒音トラブル側】が考えていること
・子どもは騒ぐもの。うるさいと思う方がおかしい。
・子どもは大きな声を出してもしょうがない。うるさいと言っても聞かないから。
・昔も今も、子どもはうるさく過ごしてきた。うるさいのは元気の証。とても良いこと。
・庭は敷地内だから、何をやっても良い。どんなにうるさくしても、誰にも言える権利はない。
・マンションではなく、一戸建てだから、騒いでも構わない。
・周りがうるさいと思うのであれば、シャッターを閉めたり、耳栓をすればいい。子どもが気を遣う方がおかしい。
・子育ては地域ぐるみで行うべきもの。だから、多少うるさいと思っても、育児の一環だと思ってもらうのが当たり前。
・うるさいと思うのは、繊細すぎるだけ。繊細な人が悪い。
・そもそもうるさいと思っていない。
※一般家庭ではなく、あくまでもトラブルを引き起こす家庭です。
騒音トラブル家庭の近所の人【被害者側】が考えていること
・うるさくすることが悪いと思うべきだ。
・子どもだからうるさくしていいとは、全く思っていない。
・子どもがうるさいわけだが、全てはその保護者に責任がある。保護者が対策するべきである。
・子どもが悪いとは思っていない。保護者が悪い。
・クレームを言われているのが分かっているのならば、対策をするべき。非常識すぎる家族だ。
・騒音が酷すぎて、精神的におかしくなりそうだ。頭痛もする。吐き気もする。気持ち悪い。
・世の中からビニールプールが無くなればいいと思う。
・なぜ、周りが我慢しなければならないのか。
・道路で遊ぶなんて、うるさいだけではない。危なすぎる。公園で遊んで欲しい。
・苦情を言われて、なぜ同じことを続けるのか。騒音が人を苦しませていることが理解できないのか。
・相手の気持ちを汲み取ることができないなんて、想像力がなさすぎる。
このように、トラブルを引き起こす方と、被害者側では、子どもの声に関する考え方に乖離があります。
そして、一旦、騒音トラブルが起きると、歩み寄るのは、はっきり言って困難です。なぜなら、人は変わることが難しいからです。人の性格を変えることは本当に大変なことです。
一方で、 騒音トラブルは、苦情を申し出た方も、言われた方も、双方が「自分が被害者である」と思っている傾向にあるといいます。
苦情を申し出る人の⼼情を察することができないと、相手との関係性がこじれてしまうことがあります。⼀般的に苦情を申し出る人は自分を被害者だと感じていますが、同時に、苦情を受けた側の心情としても、自分たちが被害者であると捉えがちです。
引用:子ども施設と地域との共生に向けて-子ども施設環境配慮手引書-(大阪府)
これまで、騒音トラブルを原因として、数々の悲惨な事件が起きてきました。双方にとって、とても悲しいことです。そのような事件に発展する前に、今回の記事では、親が配慮するべきことを探っていきたいと思います。
子どものいる家庭ですべき対策
騒音トラブルを回避する根本的な考え方
他の人に対して迷惑にならないか、相手の立場になって配慮すること。
暮らしているのは、自分たちだけではないということを自覚すること。
まずは、基本的な考え方として、相手の立場になって考えましょう。そして、住宅街に住んでいるのであれば、暮らしているのは自分たちだけではないということをしっかりと自覚しましょう。この基本的な考え方を持つだけで、騒音トラブルは回避できる確率は高まるはずです。
具体的な騒音トラブル回避対策
①子どもには、大きな声で騒がないように、しっかりと伝える。
(周りには、様々な暮らし方をしていて、子どもが騒ぐことで迷惑になることがあると、しっかりと理由まで伝える。)
②家の中では、大きな声で遊んだりしてしまう傾向があるので、窓を開けっ放しにしない。(わが家は24時間換気扇を回して、家の中の空気の循環をしています。)
③住宅街では、ビニールプール・花火・BBQの使用をしない。
④マンション・アパートに住んでいるのであれば、戸建てよりも、一層配慮する必要があるので、子どもの走り回る足音に気を付ける。防音マットには限界があるので、子どもによく言い聞かせる必要があります。
⑤常々、周りの方々に挨拶を徹底するなど、配慮している雰囲気を伝える。
騒音トラブルは危険
騒音トラブルは、今に始まったわけではありません。昔から騒音に関するトラブルは起きていました。そして、トラブルに関する悲惨な事件も以前から繰り返し起きていました。精神的に追い詰められた状況下では、冷静な判断ができなくなることもあります。
騒音トラブルは、双方の思いやりが必要となります。
特に、苦情が発生した時点で、しっかりと事実を受け止め、「子どもだからしょうがない」と決して甘く見ないようにしましょう。
まとめ
コロナ禍で、騒音トラブルが多発しています。学校が休校になったり、習い事が休みになったり、子どもが自宅にいる時間が長くなっています。一方で、大人も同様に、仕事を自宅で行うようになったり、仕事場が休業中にならざるを得ないケースも出ています。
したがって、今までにないような、誰しもが自宅にいる時間が長くなっている状況なのです。未曾有の世界的な危機的状況下では、将来の先行きや経済面、健康面等様々な問題に対して、誰しもが不安に陥っているのです。
閉塞感の漂う中で、人々が感情的になる傾向にあるのは否めません。イライラしがちな環境下で、騒音トラブルが発生するとどうでしょうか。子どもに八つ当たりすることは決して許されるものではありませんが、子どもの大騒ぎの声で、精神的に不安定になることはあり得ると思います。
コロナ禍であるからこそ、みんなで思いやりのある生活を送りたいものです。緊急事態宣言下では、子どもも遠出して遊べているわけではありません。大人も同様です。遠出してリフレッシュ旅行ができているわけではありません。
騒音トラブルは、誰にでも起こりうることです。でも、周りへの配慮をするだけで、トラブルの可能性は大きく軽減するはずです。