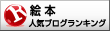災害を心配するお母さん
「地震が起きたとき、子どもは一人で対応できるのかしら…」
「子どもに災害対策をどのように教えたらいいのかしら…」
「共働きで、夫婦ともに不在のときがある…」
日本は災害大国です。
地震をはじめとして、台風、豪雨、暴風、竜巻など多くの自然災害が日本各地で頻発しています。
国内において、さまざまな災害が多発している中、安心できる地域はなかなかないと言っても過言ではありません。
したがって、日本国内に住む以上、あらゆる人が、自身で災害対策を講じることが求められます。
さらに、子どもがいる家庭においては、避難グッズを用意するとともに、「オムツや粉ミルク」など「なければならない」ものがある場合、しっかりとストックしておきましょう。
親子で、防災教育を行いましょう。
そして、親子で一緒に、万が一の行動を「考えること」が必要です。
防災教育のありかた

内閣府では、防災教育をこのように定義しています。
防災教育は、究極的には命を守ることを学ぶことであるが、そのためには、災害発生の理屈を知ること、社会と地域の実態を知ること、備え方を学ぶこと、災害発生時の対処の仕方を学ぶこと、そして、それを実践に移すことが必要となる。
そして、文部科学省では、防災教育を次のような目的を掲げています。
・自然災害について理解を深め、適切な意思決定や行動選択をできるようにする
・災害の危険を理解して自らの安全を確保する行動や日常の備えができるようにする
・学校や家庭、地域の安全活動に進んで参加し、貢献できるようにする
そして、「生きる力」を養い、防災に対応することのできる人材を育成するために、下記の4つの能力が必要としています。
1.それぞれの地域の災害の特性を知り、減災に必要な準備をする能力
2.自然災害から身を守り、被災後の生活を乗り切る能力
3.他の人々や地域の安全を支えることができる能力
4.災害からの復興を成し遂げ、安全・安心な社会を構築する能力
国として、生徒・学生にこのような指針を取っています。
一方で、未就学児の子どもには、同様の能力が「親子で」求めれられることになります。
未就学児であろうとなかろうと、「災害は待ったなし」で起こりうるのです。
つまり、未就学児であっても、「生きる力」を養うことが求められるのです。
そのためには、親子でしっかりと話し合って、対策をしましょう。
親が子どもに伝えるために

家族と話し合おう
内閣府の世論調査(平成29年)では、災害に対する認識を調査された結果があります。
<ここ1~2年ぐらいの間に、家族や身近な人と、災害が起きたらどうするかなどについて、話し合ったことがあるか>
・「ある」・・・・57.7%
・「ない」・・・・41.7%
<どのようなことを話し合ったか>
・「避難の方法、時期、場所について」・・・・68.2%
・「家族や親族との連絡手段について」・・・・57.8%
・「食料・飲料水について」・・・・・・・・・55.3%
・「非常持ち出し品について」・・・・・・・・41.7%
「家族や身近な人と、災害が起きたらどうするかなどについて、話し合ったことがあるか」という問いに対して、「ない」という回答が41.7%あります。
どのように伝えるべきか
子どもに伝えるには、まず災害に対するイメージを掴んでもらうことが大事です。
そのためには、NHKの動画で、子ども向けの分かりやすい動画があります。
また、地震が起きたときに、どのように行動するべきか、丁寧に描かれた絵本もあります。
娘には、定期的に「じしんのえほん」を読み聞かせながら、机の下にもぐらせるなど、動きながら学ぶようにさせています。
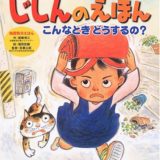
考えよう
子どもに、災害に対するイメージを掴んでもらうことができたら、次に、何をするべきか話し合いましょう。
最初から子どもに対して、指示したり教えるのではなく、「自分で何をするべきか」考えてもらいましょう。
万が一の際、「いつも」親がいるとは限りません。
たまたま、何らかの理由で、「一人で」いる可能性もあります。
それでも、落ち着いて行動するためには、一人で考え抜く力があるかどうかで、生きられるかどうかが変わってくるのです。
したがって、話し合いの場において、いかに当事者意識を持つことができるかどうかが鍵になります。
これは、何歳であっても、考え抜く必要があります。
小学生から考えればいいのではなく、未就学児であっても、「自分自身で」考える必要があります。
繰り返しますが、未就学児であろうとなかろうと、「災害は待ったなし」で起こりうるのです。
未就学児であっても、「生きる力」が求められます。
親が備えるために
内閣府の世論調査では、「非常持ち出し品について」について話し合いがされたのは、41.7%です。
ぜひ、ご家庭で、避難がすぐさまできるように、リュックなどを用意しておきましょう。
わが家では、万が一のことが起きたとき、避難がスムーズにできるように、玄関の一角に避難用リュックを置いています。
また、何らかの事情で、玄関にたどり着くことができないことを想定して、2階の寝室にも、避難グッズを用意しています。
あらゆることを想定することが大事だと思いますが、まずはできることから始めましょう。
避難グッズを揃えていない方は、まずは一つを用意しましょう。
そして、一つ避難グッズを準備してある方は、さらにステップアップ。
避難グッズを用意してある部屋から、一番遠い場所あるいは一番長く滞在する部屋に、もう一つ避難グッズを用意しておくと安心です。
もし、「何を揃えておけばいいのか分からない!」ということであれば、
まずは、一つ一つ用意を進めておきましょう。
災害は「いつ」起きるか分からないものです。
念には念を入れて、準備を怠ることなく、家族でしっかりと話し合いましょう。