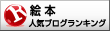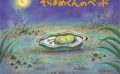雪害では、どのような災害が起こるのか

雪害の代表的ものとしては、雪崩、除雪中の転落事故などの豪雪地帯特有の災害のほか、路面凍結などによる交通事故や歩行中の転倒事故など、豪雪地帯以外でも発生する災害・事故があります。
また、雪の降る地域の住民だけでなく、冬山登山やスキー、観光などで豪雪地帯を訪れる多くの人々も被害に遭っています。雪害に遭わないためにも、雪に対する正しい知識を深めておくことが大切です。
下記の5つのケースに分けて、雪害を説明していきます。そして、今回の記事では、雪崩による事故に絞ってお伝えします。
1.除雪中の事故
2.車による雪道での事故
3.歩行中の雪道での事故
4.雪のレジャーでの事故
5.雪崩による事故
雪崩とは
雪崩とは、「斜面上にある雪や氷の全部又は一部が肉眼で識別できる速さで流れ落ちる現象」を言い、積雪が崩れて動き始める「発生区」と、発生した雪崩が通る「走路」、そして、崩れ落ちた雪が積み重なる「堆積(たいせき)区」からなっています。また、雪崩によって堆積した雪を「デブリ」と呼びます。
なお、雪崩は“すべり面” の違いによって、「表層(ひょうそう)雪崩」と「全層(ぜんそう)雪崩」の大きく2つのタイプに分けられます。
雪崩災害に遭わないために

雪崩はとても速く、発生に気付いてから逃げることは困難です。身を守るためには、前もって雪崩が発生しやすいケースを知っておくことが重要です。日頃から危険箇所や気象情報をチェックし、雪崩の前兆を発見したらすぐに最寄りの市町村役場や警察署へ通報してください。
<発生しやすい場所>
・急な斜面
一般的に、スキーの上級者コースと同程度の30度以上傾斜になると発生しやすくなり、特に35~45度が最も危険と言われています。
・「落石注意」の標識が設置場所
・高木が密に生えている斜面では雪崩が発生しにくい一方、低木林やまばらな植生の斜面では雪崩発生の危険が高くなります。笹や草に覆われた斜面などは裸地よりも発生しやすい地形です。
<発生しやすい条件>
・気温が低く、既にかなりの積雪がある上に、短期間に多量の降雪があったとき
・急傾斜で、特に雪庇(せっぴ)や吹きだまり(雪が風で吹き寄せられ堆積した場所)
・0度以下の気温が続き、吹雪や強風が伴うとき
・過去に雪崩が発生した斜面など
・春先や降雨後、フェーン現象などによる気温上昇時
・斜面に積雪の亀裂ができている場所など
<普段から心がけるべき事発生しやすい条件>
・市町村が作成、配布するハザードマップによって、その地域の危険箇所を把握しましょう。
お住まいの都道府県又は市町村のホームページで危険箇所を確認できます。
・気象庁が発表する「なだれ注意報」などの気象情報が出ていないかを確認しましょう。
雪崩発生の場に遭遇したとき
<雪崩が自分の近くで起きた場合>
1. 流されている人を見続けること。
2. 仲間が雪崩に巻き込まれた地点(遭難点)と、見えなくなった地点(消失点)を覚えておく。
3. 雪崩が止まったら見張りを立て、遭難点と消失点にポールや木などの目印をたてる。
4. すぐに雪崩ビーコン(無線機)などを用いて、捜索する。
5. 見つかれば、直ちに掘り起こして救急処置を行う。
<自分が雪崩に巻き込まれた場合>
1. 雪崩の流れの端へ逃げる。
2. 仲間が巻き込まれないように知らせる。
3. 身体から荷物を外す。
4. 雪の中で泳いで浮上するようにする。
5. 雪が止まりそうになったとき、雪の中での空間を確保できるよう、手で口の前に空間を作る。
6. 雪の中でも、上を歩いている人の声が聞こえる場合があるため、聞こえたら大きな声を出す。
参考資料
・首相官邸HP