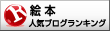悩む少年
「勉強、勉強、勉強。お母さんによく叱られてやる気が出ないよ。それに、勉強なんてつまらないし…」
親に「勉強しなさい」と言われ続けてしまうと、子どもは委縮するなどして、やる気を失います。
皆さんも、多少思い当たることがありませんか。なぜ、「しつけ」と称して、親の価値観を子どもに強いることをしてしまうのでしょうか。
解決策を探っていきます。
そして、その過程で、「怒る」「叱る」「注意する」「諭す」の違いについても考えましょう。
躾(しつけ)とは
躾(しつけ)をする。
まず、どういう意味なのか、漢字辞典で「躾」の意味を確認してみます。
躾(しつけ)
漢字源より
<意味>
①しつけ。身についた礼儀作法。身だしなみ。
②しつける。礼儀作法を教えこむ。
<解字>
「身+美」の日本製の漢字。からだを美しく飾ることから、しつけの意をあらわす。
子どもが成長するために、親は多くのことを教えていきます。
漢字辞典にある通り、「躾」とは、身体を美しく飾ることから由来しています。
したがって、「躾」とは、子どもに、礼儀作法を教えるためのことを意味しており、親が望んでいることを押し付けることではありません。
親の価値観
幼児期・小学校低学年を前提に話を進めていきます。
立場上、「親」と「子」の関係は、「親」が圧倒的な存在となります。したがって、多くの場合、「親」の言うことは「絶対的」になるはずです。
親子共に、信頼関係を構築することができていれば、問題はありません。しかし、理不尽な指示を押し付けると、親子の信頼関係は崩れ、子どものやる気がそがれます。
親の側面
親が高学歴・高収入である場合、子どもの頃に努力して勉強をしてきた傾向が強いです。自分が努力を続けて成果を上げると、自分の子どもにも、その努力を強要してしまいがちです。
しかし、子どもは一人の人間であり、親の所有物ではありません。
そして、育ってきた過程も異なるのだから、能力差もあって然るべきです。つまり、子どもに自分のやってきた努力を押し付けてはいけないのです。
大半の場合、親が高学歴・高収入であると、自分が歩んできた道は正しいと思い込んでおり、また、親自身が真面目な性格であれば、子どもにも良かれと思って押し付けてしまうのです。
親は真面目であればあるほど、子どもの教育を本気で考えているので、努力を強要することが悪いとは思っていません。そこは、気を付けなければならない点です。
優秀な成績で子ども時代を過ごしてきて、現在、育児をしている方を見てみると、次の大きく二通りがあるように思えます。
・子どもの教育を本気で考えているが故に、「努力」を子どもに強要してしまう人。
・子どもを「信じて」いて、子どもがやりたいことを、ひたすら「見守り」、ただただ応援してあげる人。
子どもを信じてあげられるかどうか。
「子どもを信じる」ことは、「子どもを伸ばす」ことに繋がるのではないかと思います。
子どもの側面
親が愛情を持って子どもを育てていると、子どもは親を好きになります。
そして、子どもは親が喜ぶ姿を見せようとします。健気な子どもは、親が子どもに対して喜ぶ姿を見たいのです。
したがって、子どもは親の期待に応えたいと頑張ります。
しかし、あまりに度が過ぎる期待は、子どもを追い詰めたり、心が折れてしまうことがあるので、気を付けなければいけません。
そして、その期待が日常的になると、子どもはやる気をそがれることになります。場合によっては、親の言うこと全般、耳を傾けない事態に陥りかねません。
筆者は、天邪鬼の性格で、筆者の親はその性格を見抜いていたようで、学生時代に一度も「勉強しなさい」と言われたことがありませんでした。
親は、子どもと同じ土俵に立たず、そっと子どもの成長を見守り、困ったことがあったときに、すぐ手を差し伸べるようにしておけばいいのではないでしょうか。
「怒る」「叱る」「注意する」「諭す」の違い

子どもを育てるうえで、避けて通れないのが、子どもを叱ること。しかし、親が叱るとき、ついついイライラして感情的になることはありませんか。
個人的には、親も人間ですし、聖人ではありませんので、仕方ない部分はあると思います。
まずは、国語辞典でそれぞれの語彙を確認しましょう。
怒る(おこる)
新明解国語辞典第4版
①がまん出来なくて、不快な気持ちが言動に表れた状態になる。
②目下の者などのやり方が悪いと言って、強い言葉でしかる。
叱る(しかる)
新明解国語辞典第4版
相手の仕方を、よくないといって、強く注意する。
注意(ちゅうい)
新明解国語辞典第4版
①大事な点や微妙な変化などを見落としたり何かをする時にやり損じをしたりしないように、気をつけさせたりすること。
②不結果に陥るといけないので十分に気をつける(ように、相手に気をつけさせる)こと。
諭す(さとす)
新明解国語辞典第4版
下の者に、事の理非をよく分かるように教える。
言葉の意味がそれぞれ違いがありますが、親の「発信方法」と子どもの「受け止め方」はどちらにしても同じです。
「怒る」ことはダメで、「叱る」ことは冷静に。などと言うことがありますが、どちらにしても子どもからすると、叱られるものは嫌なものです。とは言え、「ダメなものはダメ」と伝えなければいけない場面はあります。
「親」は、「子どもの友達」ではありません。
「怒る」「叱る」「注意する」「諭す」の違いを気にするのではなく、しっかりと子どもに「伝えるものは伝える」。
冷静に淡々と、子どもに話し合う必要があるのではないでしょうか。
まとめ
「しつけ」と称して、親の価値観を子どもに強いる。優秀な成績を修めてきた親にありがちですが、それは、きっと子どもの将来を真剣に考えているからこそです。だからこそ、なぜ子ども時代の自分のように、「もっと努力しないのだ!」と憤慨するのでしょう。
私への戒めでもあるのですが、繰り返します。
子どもは子ども。あなたはあなた。
DNAの関係は多少あるでしょうが、時代・教育・周りの友達など、全てが親とは環境が異なるのです。そこをしっかりと理解して、子どもを信じて、応援してみてはいかがでしょうか。
まずは、私も、子どもを信じてあげたいと思います。